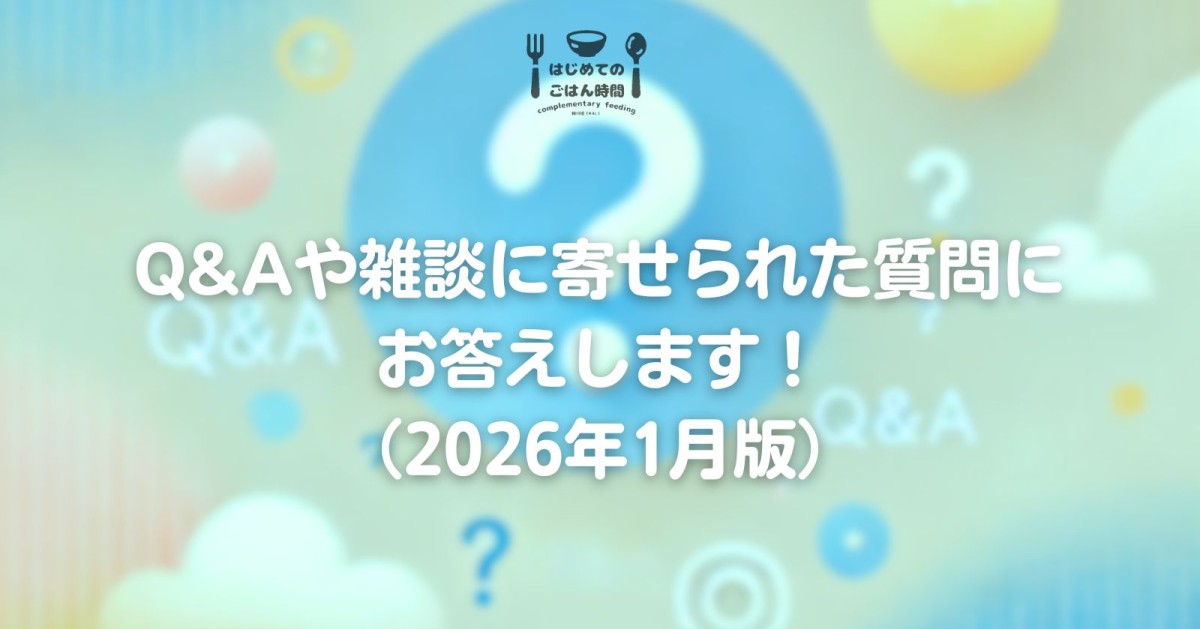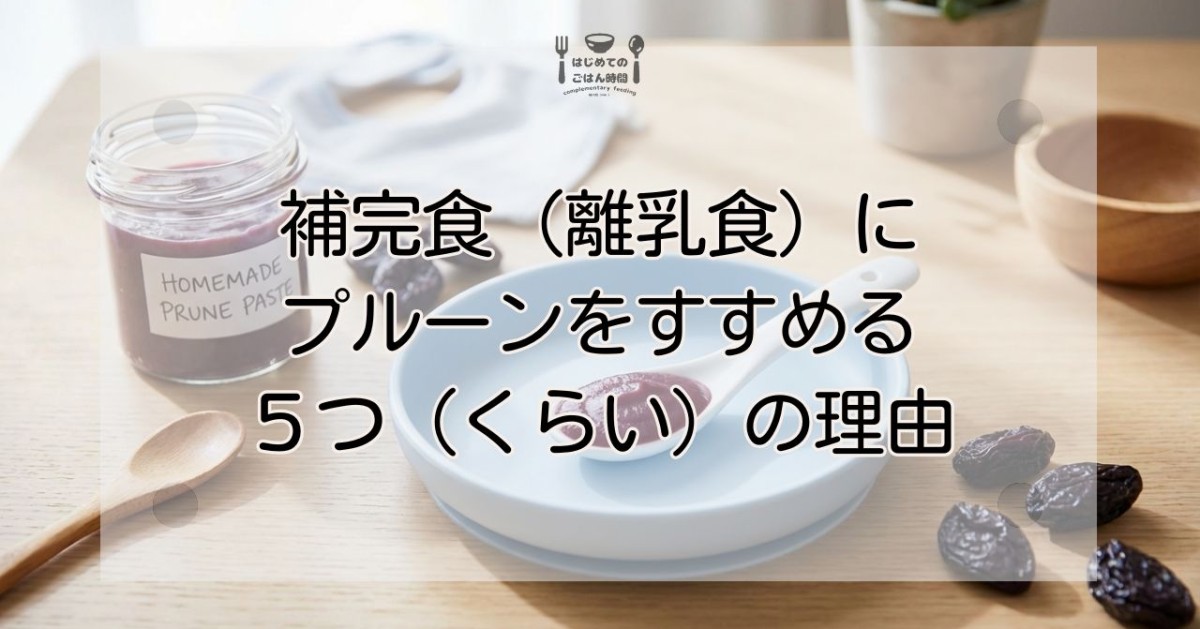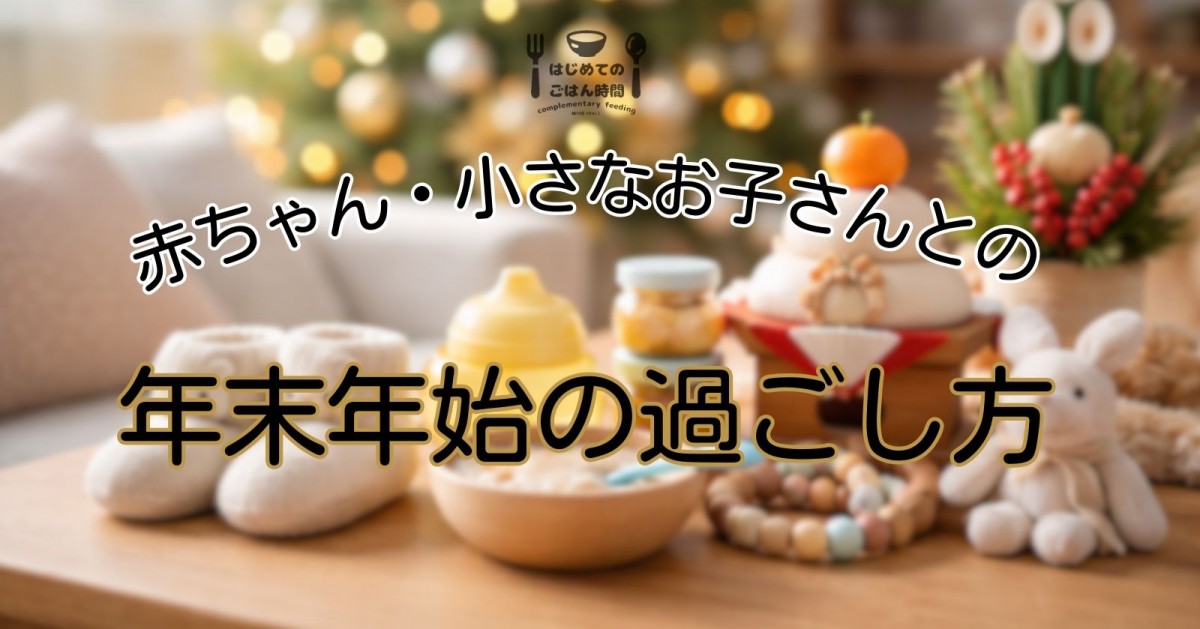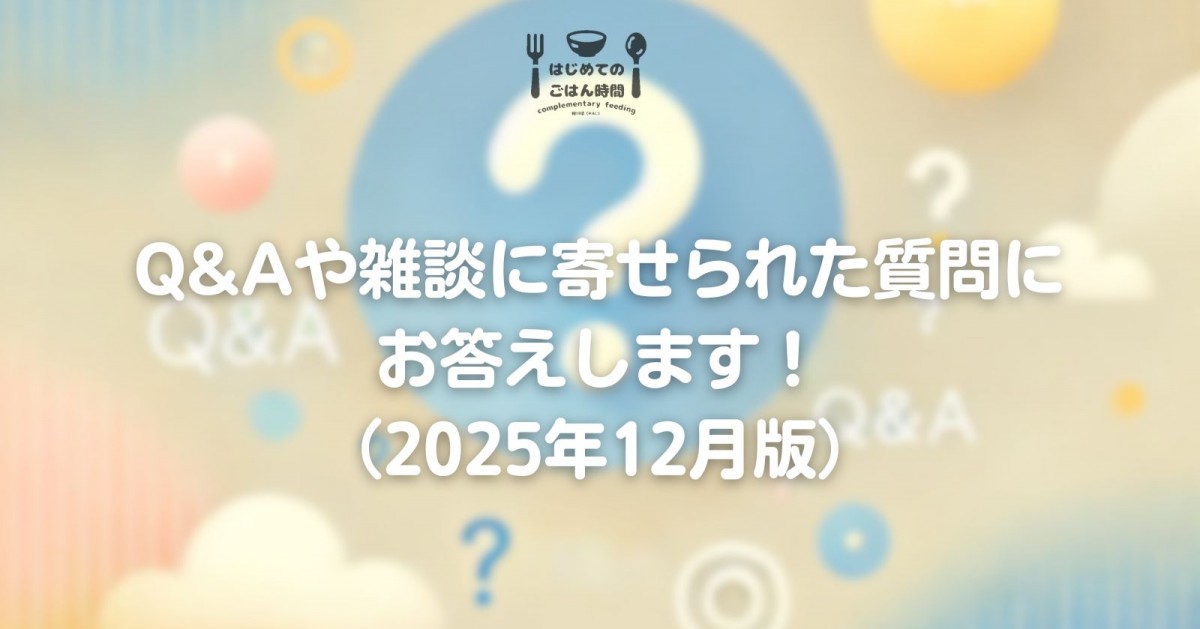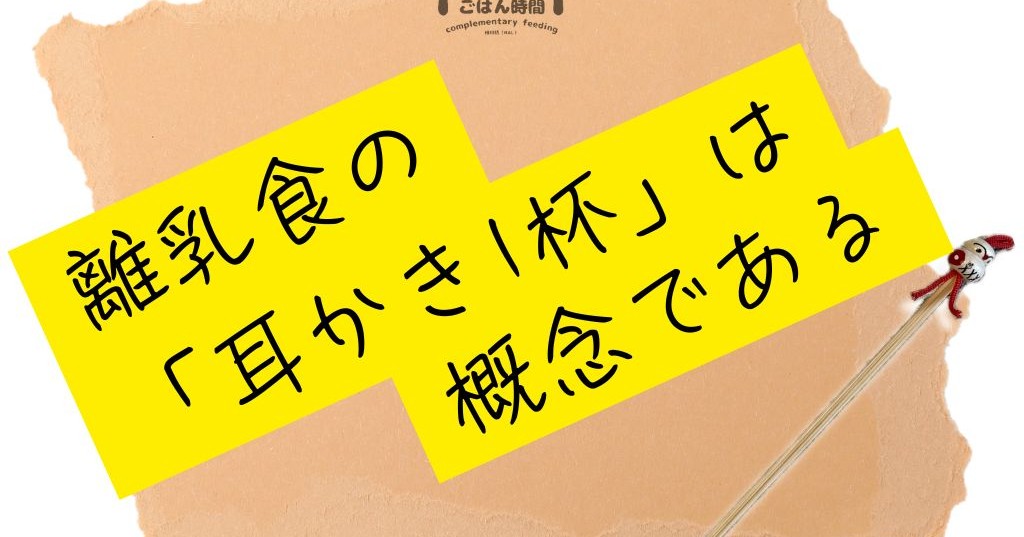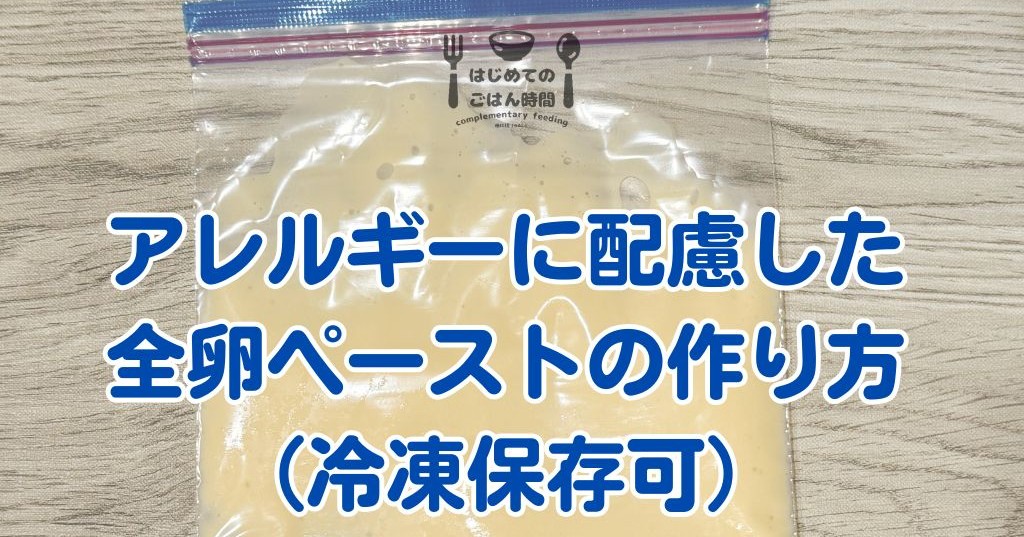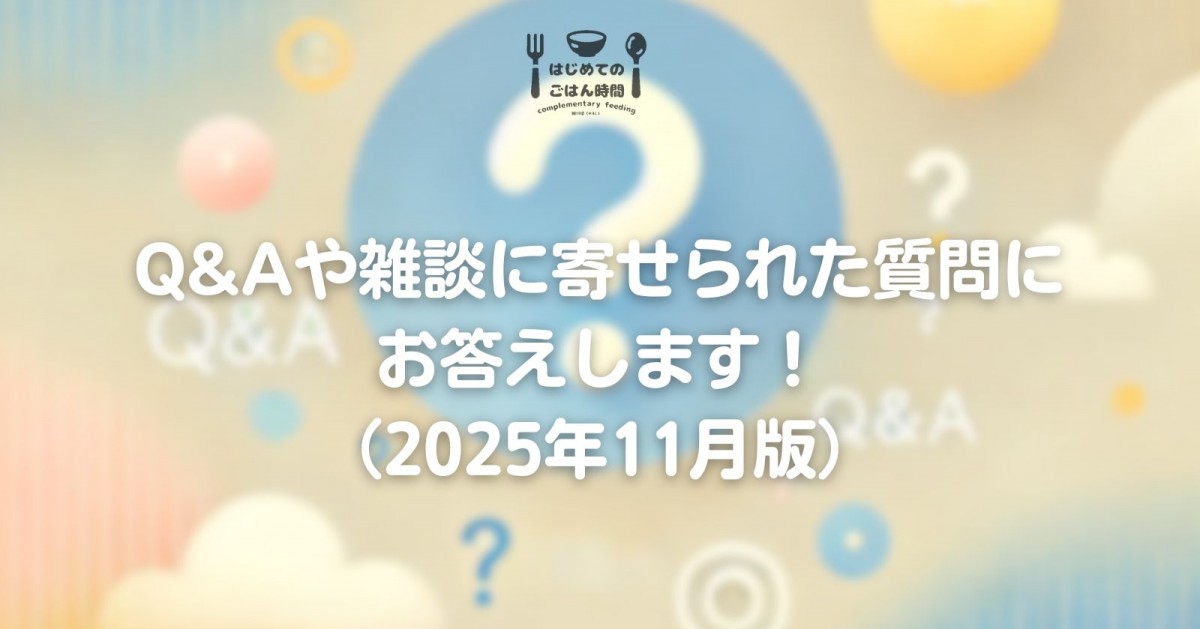補完食(離乳食)からのナッツ類の具体的な導入方法(前編)
こんにちは、相川晴です。
さて今回は、前回に引き続き、ナッツのお話をしていこうと思います。
前回、ナッツ(木の実類)アレルギーが日本で増えてきているよーというようなお話をしました。
それでは、実際にナッツ類をどうやって補完食(離乳食)、もしくはそれ以降に導入したらいいのか? 最初の量や増量方法、摂取間隔、摂取期間をどうしたらいいのか――という大変具体的な話をしていこうと思います。

(むっ……ロゴの周りを白抜きにした方がよさそうだな……)
そもそもナッツ類を補完食の時期に導入できるんかいな、というところも書いてますし、どのナッツを優先したらいいかという話にも踏み込んでいきます。
もう子どもは大きくなったけど、そういえばまだナッツを試したことがないな……という方にも読んでいただけると嬉しいです。(とにかく最初の量を少なくスタートするということだけでも覚えててください!)
本当は一つのレターにまとめる予定だったのですが、あまりに悩み過ぎたせいか1万字を軽く突破してしまいました……
こんなレターを送りつけられたら読む方もたまらんだろう、ということで、前後編に分けてお伝えしたいと思います。長くなってすみません。もう後編もほぼできてますので、数日中に配信いたします。
ナッツ類アレルギーを補完食(離乳食)早期に導入する意義がどのくらいあるかについては、前回の記事の最後の部分にも書いていますのでご一読ください。
まず前提条件として、
分類上、ピーナッツはナッツ類ではない
です。
ピーナッツはあんな風貌をしてますが、分類としてはマメ化ラッカセイ属、要するに豆類です。Official髭男dismの「ミックスナッツ」でも”袋に詰められたナッツのような世界では””そこに紛れ込んだ僕らはピーナッツみたいに木の実のふりしながら微笑みうかべる”って歌詞がありますが、木の実ではありません。
ナッツ類もナッツ類といいつつ、生物学的な分類が全然違うものになってきます(なので、どれかナッツのアレルギーがあったとしても、食べられるかもしれないからまとめて除去しないでほしい……)

筆者作成
こんな感じ。
(今回のナッツの導入の話のように、誤解を招きやすい内容、周辺情報をしっかり書いた上でお伝えしたい内容は、切り抜きで拡散されたくないと思ってましてサポートメンバー限定記事としております。今後もメアド登録のみで無料で読める記事を中心に、サポートメンバー限定記事も挟み込みながら発信していきます。サポートしていただけるとめちゃくちゃやる気が出ますので、ちょっとお高いコーヒー1杯分なら……と思ってくださる方、よかったらお願いします!)